経営計画を経営力の向上に役立つものとするには、組織的にPDCAマネジメントサイクルを回すことができるよう、会計システムを整備しておかねばなりません。
具体的には、「部門別の月次損益計算書を、予算と実績を対比させて作成する」ように会計システムを構築するのですが、前回はまず、部門別損益計算書のしくみを整備するための注意点について書きました。
今回は、月次損益計算書を作成するための会計システムを構築する際の注意点について書きます。
経営者の口からよく「月初に前月の成績を知りたいのだけど、月の半ばを過ぎなければ経理から損益計算書が出てこない。」というグチを聞くことがあります。
ひどい会社になると、「一年の決算を終えなければ会社が儲かっているのかわからない。」という状況があったりします。
このような状況では、“毎月定期的にPDCAマネジメントサイクルを回して経営管理を行う”といったことはとてもできません。
何が良かったか、何が悪かったかもハッキリわからず、改善のポイントも絞れません。
PDCAマネジメントサイクルを回して経営力の向上に役立てるためには、管理を行う人に毎月、できるだけ早いタイミングで管理するための資料を提供しなければなりません。
前月の売上成績は、翌月の1日に、損益状況は、遅くとも翌月の中旬までに、管理を行う人に分かりやすいデータとして届けなければならないのです。
ところが、今までこのことの必要性を感じていなかった会社においては、管理に役立つ会計資料をこうした早いタイミングで提供するのは容易ではありません。
「忙しくて伝票を処理するのが遅れる」「仕入先からの納品書が届くのが遅い」「毎月棚卸するような時間は無い」など、早くできない理由を言う人は沢山います。
仕事のできるキーマンに仕事が集中し、そのキーマンがこうした“できない理由”を述べるケースは特にやっかいです。
月次損益を早く出すためには、トップの強い意志が不可欠です。
「何が何でも、売上は翌月の1日に、損益は翌月の10日までに出すように!」「そのために何をしなければならないか考えよ!」と断固とした意志で号令をかけるのです。
中期経営計画の重点施策にそのことが入っており、そのしくみを構築する担当部門が決まっていれば、なお望ましいと言えます。
月次決算は、本決算と違って、精緻さは必要ありません。要点を押さえた正確さとスピードが命です。
月次決算のための会計システムを構築する人は、そのことを肝に銘じてしくみやルールを作らねばなりません。
具体的には、例えば次のような点に注意を払って構築するのが良いでしょう。
【売上高】
売上高は、最も重要な指標であり自社社員ですぐに把握できるものなので、翌月の1日に集計しなければなりません。売上値引があれば、その金額も含めます。
重点商品を設定していれば、その販売台数等も含めて、月初の朝礼などで発表できるしくみを作るべきです。
手作業であっても集計方法を工夫し、それでも無理だと判断した場合は、コンピュータシステムの導入をためらうべきではないでしょう。
【売上原価】
月次損益を早期に提供するために重要かつ難易度が高いのは、売上原価を正確に計算することです。
仕入の計上は、仕入先からの請求書の到着を待っていてはかなり遅れてしまうので、納品書ベースか、現物ベースで仕入高を計上するしくみを構築します。
さらに難しいのは、月末の棚卸高を計算することで、在庫を持つ事業を行う会社は、帳簿在庫で月次決算を行うか、現物在庫で月次決算を行うか、自社の商品と現場の状況を良く分析して適切な方法を選択しなければなりません。
売買利益がいくらであったかは、月次損益計算上きわめて重要な指標ですので、売上原価は売上高に対応させて発生基準で計上します。
時間がかからず、かつ大要を押さえた損益がつかめるよう、システム化に知恵を絞ります。
【管理販売費】
管理販売費は、月次決算では概ね支払基準で計上しても良いでしょう。家賃や給料などは、毎月ほぼ一定の金額が発生しますし、広告宣伝費や運賃などの月によって変動する科目であっても、翌月の支払い時に反映されるので支払基準でも問題は少ないでしょう。
毎月、未払金を計上する手間を考えると、支払基準で計上するルールとした方が望ましいケースが多いと思われます。
ただし、月割費用引当金勘定を用いて、支払の発生しない月の費用を仮計上した方が、月次損益を見る場合に判断を誤らすことなく望ましい科目があります。
一つは、期の初めの月の管理販売費で、決算月に未払金を計上するため、支払ベースでは期の初めの月の費用がほとんど発生しなくなってしまう科目です。
もう一つは、賞与や減価償却費などで、特定の月だけ多額の費用が計上されることがあらかじめ分かっている科目です。
こうした科目については、毎月ほぼ定額に費用が計上されるよう、月割費用引当金勘定を相手科目として一月分を計上し、発生月や決算月に取り崩す方法で毎月の費用計上を平均化させます。
こうして月次決算を早く提出するための新しいしくみやルールを作っても、最初の内はなかなか早く月次決算書を作成することはできません。
現場の人の作業について従来のやり方を変えるのは一筋縄ではいかない場合が多く、全員の意識改革が進まないと誰かがボトルネックとなって、月次決算全体のスケジュールを遅らせてしまうからです。
会計システムは構築するだけでなく、それを効果的に働かせるための現場の意識改革とたゆまぬ改善作業が欠かせません。
新しい会計システムを使って、毎月、PDCAマネジメントサイクルを回し続けることで、会計システムの改善点も見えてきてほんとうに役立つシステムに育ってくるのです。
月次決算を早く行うことは、PDCAマネジメントサイクルを回して経営管理を効果的に行うことが目的ですが、早めの資金繰り表の作成や早期の決算対策へも活用できるので、会社経営に多くの好影響が期待できます。
まだ対応できていない場合は、早急に着手されることをお勧めします。
| このような経営計画は役に立たなくなる可能性があります |
⇩
| その㊱ |
| 月次決算を行っていない、又は出すのが遅い。 |
経営計画策定のコンサルティングを行っています➡【問合せ】
役に立つ経営計画はオーダーメイドです。どんなサポートをお求めか「問合せ」てください。
★このページとの関連の深いページ
予実管理(1) 〜PDCAマネジメントサイクル〜
予実管理(2) 〜部門別損益計算書〜
予実管理(4) 〜比較損益計算書〜
予実管理(5) 〜比較損益計算書の分析〜
★経営計画のヒントの全体構成
自社の分析 経営計画の骨子 重点施策と活動計画 KFSの点検 損益計画 貸借対照表計画 資金繰り計画 全体の整合性確認 推進体制づくり 予算化 予実管理

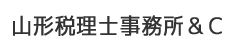












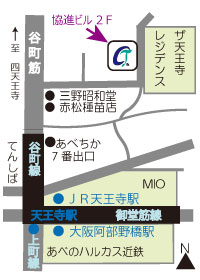



 ロゴについて
ロゴについて